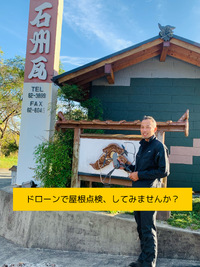YANEノート動画 【凍害編】
石州瓦紹介動画 第3弾
今回は凍害について

石州瓦が寒さに強い瓦という事が分かる動画です。
九州ではあまりなじみの無い「凍害」
石州瓦の故郷の島根県は冬は雪が多く寒い地域になります。
海外でもロシアでの施工実績もあります!!
過酷な環境下でも耐えうる、品質なのです。
今回は凍害について

石州瓦が寒さに強い瓦という事が分かる動画です。
九州ではあまりなじみの無い「凍害」
石州瓦の故郷の島根県は冬は雪が多く寒い地域になります。
海外でもロシアでの施工実績もあります!!
過酷な環境下でも耐えうる、品質なのです。
隣が火事の現場へ点検へ
工務店さんからの依頼で、
「先日、佐賀市内で火事が発生した現場の隣がウチが建てた所だから、点検に行ってくれ。」
早速確認へ。
屋根瓦は異常無し!!
しかし、雨樋の集水部の漏斗がプラスチック製の為に

グニャリ。(わかりにくいですが…。)
火災時の温度より高い温度で焼かれてる瓦が負けるわけないですね!!
火災が起きないのが一番ですが…。
屋根から隣の火事の現場を見ましたが、ゾッとしました。
「先日、佐賀市内で火事が発生した現場の隣がウチが建てた所だから、点検に行ってくれ。」
早速確認へ。
屋根瓦は異常無し!!
しかし、雨樋の集水部の漏斗がプラスチック製の為に

グニャリ。(わかりにくいですが…。)
瓦は高温で焼いて作られます。それにより火災の延焼防止にもなるんです。
火災時の温度は最高温度が1200℃を超えると言われています。少し距離が離れていても、840℃くらいの炎が襲ってきます。しかしは、1000℃以上の高温で焼き上げられている不燃材なので燃えないんですよ〜。
愛知県陶器瓦工業組FaceBookページより
火災時の温度より高い温度で焼かれてる瓦が負けるわけないですね!!
火災が起きないのが一番ですが…。
屋根から隣の火事の現場を見ましたが、ゾッとしました。
YANEノート動画 石州瓦ってどんな瓦?
石州瓦紹介動画 第2弾
今回は石州瓦の歴史について紹介されてます。

小瓦の箸置き
石州瓦の代名詞「赤瓦」をイメージされると思います。
年配の方は石州瓦の事を「甕(かめ)瓦」と言われる所以が分かりますね。
今回は石州瓦の歴史について紹介されてます。

小瓦の箸置き
石州瓦の代名詞「赤瓦」をイメージされると思います。
年配の方は石州瓦の事を「甕(かめ)瓦」と言われる所以が分かりますね。
YANEノート動画 オープニング
石州瓦工業組合(島根県)が、
石州瓦の事を良く知ってもらおう!!
と、制作された動画です。

今回はオープニング編
続編もあるのでお楽しみに!!
一本一本は短いので、気軽に視聴できます。
少しでも石州瓦の事を知って頂ければと思います。
石州瓦の事を良く知ってもらおう!!
と、制作された動画です。

今回はオープニング編
続編もあるのでお楽しみに!!
一本一本は短いので、気軽に視聴できます。
少しでも石州瓦の事を知って頂ければと思います。
練習中!!
11月29日の九州かわらぶき技能競技会へ向けて、休日返上で練習中。
数年振りの、架台で思い出しながらの練習。
とにかく、やれる分やってみる!

数年振りの、架台で思い出しながらの練習。
とにかく、やれる分やってみる!

全日本瓦工事業連盟のお墨付き
この度、弊社は
一般社団法人 全日本瓦工事業連盟による
瓦屋根標準設計・施工ガイドライン適合施工店
に登録されました。

簡単にいうと、「丈夫な屋根を施工します!!」という事です。
特に棟の施工では㈱セラミカ㈱丸惣の防災棟(特許取得)のサンドウィッチ工法で強固な施工を提供しております。
安心・安全をお客様に提供するにあたって、従来よりやや工事金額も上がってしまいます。
巷では、弊社よりグッと安い工事金額で屋根工事をする会社もありますが、「安かろう、悪かろう」がほとんど。
屋根自体は地上から見えにくく、肝心の瓦の留め方等は瓦に隠れる部分ですので、出来上がりはどこもキレイに仕上がります。
台風等の災害時に「ありゃ、瓦が飛んで行った」とならないように、きちんとした業者を選ぶ事が大事です。
屋根工事は全瓦連に加盟店へ。
一般社団法人 全日本瓦工事業連盟による
瓦屋根標準設計・施工ガイドライン適合施工店
に登録されました。

*「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」とは何か?
・10年間の安心保障…万一、メーカーや施工業者のミスによって欠陥が見つかった場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき保証されます
・住宅性能表示制度…住宅の強度や火災時の安全性など、9項目の「住まいの性能」を規定。より安全、安心、快適な住環境を消費者の皆様に提供しています。
・厳しい施工基準…「震度7にも耐えられる」というように「性能」を明確に謳う「ガイドライン工法」には、科学的実験による実証が欠かせません。結果的に施工基準も、従来の何倍も厳しい内容になっています。
簡単にいうと、「丈夫な屋根を施工します!!」という事です。
特に棟の施工では
安心・安全をお客様に提供するにあたって、従来よりやや工事金額も上がってしまいます。
巷では、弊社よりグッと安い工事金額で屋根工事をする会社もありますが、「安かろう、悪かろう」がほとんど。
屋根自体は地上から見えにくく、肝心の瓦の留め方等は瓦に隠れる部分ですので、出来上がりはどこもキレイに仕上がります。
台風等の災害時に「ありゃ、瓦が飛んで行った」とならないように、きちんとした業者を選ぶ事が大事です。
屋根工事は全瓦連に加盟店へ。
屋根知識 第7弾
こんなのが屋根の棟に乗っている家を見かけた事ありますか?
これは、「鯱(シャチ)」と言って、飾りです。
鯱とシャチは違いますよ。海にいる方じゃないです。
屋根の飾りには、いろいろな意味があります。
今日はこの鯱について・・・。
有名なモノとして、名古屋城の「金の鯱鉾」(高さは2.6mほどあるそうです。)を一番に思い出すのではないでしょうか?
そもそも鯱とは、姿は魚で頭は虎、尾ひれは常に空を向き、背中には幾重もの鋭いとげを持っているという想像上の動物です。
(唐津くんちにも13番目の曳山でありますね。)
鬼瓦同様に家の守り神、家運の隆盛を願い、
鯱は水の神様で、「鯱が水を呼ぶ」ということで、火災にあわないように願いを込めて、棟に据えられるようです。
屋根知識 第6弾
今回は、瓦の種類について。
施工状況blogで瓦の名前が出てきてもピンとこない方が多いと思いますので、代表的な瓦を紹介します。

屋根を空から見下ろした図。

防災平瓦は地瓦などと呼ばれ、一番使われる瓦です。
防災唐草は③で使用する瓦です。軒瓦とも言います。
防災大袖は⑰
防災小袖は⑱で使用します。袖は地面から屋根に向かって、右が大袖、左が小袖です。
防災大角は⑩
防災小角は⑪で使用します。
以上が代表的な「地瓦」の種類です。
割熨斗(わりのし)は棟を施工する時に使用します。
これを半分に割って真中に銅線を通して積み上げていきます。
良くTVで瓦割りで使われる瓦です。が、あんなに簡単には割れないですよ。(瓦の生産地によって硬さが異なるので、当社が使ってる石州瓦じゃないです。)
七分雁振(しちぶがんぶり)は熨斗瓦を積んだ上に被せる瓦です。
以上です。
まだまだ、種類は沢山ありますが、ぼちぼち紹介していきます。
質問等ありましたら、お気軽に問い合わせてください。
では次回をお楽しみに。
施工状況blogで瓦の名前が出てきてもピンとこない方が多いと思いますので、代表的な瓦を紹介します。
屋根を空から見下ろした図。
防災平瓦は地瓦などと呼ばれ、一番使われる瓦です。
防災唐草は③で使用する瓦です。軒瓦とも言います。
防災大袖は⑰
防災小袖は⑱で使用します。袖は地面から屋根に向かって、右が大袖、左が小袖です。
防災大角は⑩
防災小角は⑪で使用します。
以上が代表的な「地瓦」の種類です。
割熨斗(わりのし)は棟を施工する時に使用します。
これを半分に割って真中に銅線を通して積み上げていきます。
良くTVで瓦割りで使われる瓦です。が、あんなに簡単には割れないですよ。(瓦の生産地によって硬さが異なるので、当社が使ってる石州瓦じゃないです。)
七分雁振(しちぶがんぶり)は熨斗瓦を積んだ上に被せる瓦です。
以上です。
まだまだ、種類は沢山ありますが、ぼちぼち紹介していきます。
質問等ありましたら、お気軽に問い合わせてください。
では次回をお楽しみに。
タグ :屋根知識
屋根知識 第5弾
今回は、瓦の種類、工法についてです。
大きく、「和」と「洋」の二つに分けられます。
「和」
・本葺き
・引掛け葺き
・その他
・本葺き―平瓦と丸瓦とを組合わせて葺く工法。日本古来の工法であり、主に寺院建築に使われる工法です。
平瓦と平瓦の接点に丸瓦を被せる工法なので、屋根の重厚感はあり、普通の瓦に比べて風にも強く、耐用年数が長い等の特徴がありますが、使用する材料が多いので、コストもあがり屋根荷重が重くなるので、それに合わせた建築構造も強固にしなければなりません。

(左)平瓦 (右)丸瓦

平瓦を敷き並べて、継ぎ目に丸瓦を並べる

・引掛け葺き―屋根下地に横方向に桟木を打ちそれに瓦を引っ掛けて葺く工法です。
現在の主流の工法で、瓦がずり下がらない、瓦を釘打ち出来るなどの丈夫さを優先した工法で、耐震・耐雪・耐風の力を発揮します。


「桟木」を打ち、それに瓦の裏の凸ちんを引っ掛けて、釘で留めていきます。

「洋」
形状は、

・平板(㈱鶴弥 スーパートライ110)

・S形(石央瓦販売㈱ ニューセラS)
の、代表的な2タイプになります。
現在、新築物件の和・洋の割合は、4:6程度で洋が多いです。
シンプルなお宅が増えて来ていますからね。
工法は引掛け葺きになりますので、「和」と施工要領は一緒です。
「和」は棟が、熨斗(のし)積み、

「洋」は丸瓦のみという感じが多いです。

不定期な、屋根知識講座。またお楽しみに!!
大きく、「和」と「洋」の二つに分けられます。
「和」
・本葺き
・引掛け葺き
・その他
・本葺き―平瓦と丸瓦とを組合わせて葺く工法。日本古来の工法であり、主に寺院建築に使われる工法です。
平瓦と平瓦の接点に丸瓦を被せる工法なので、屋根の重厚感はあり、普通の瓦に比べて風にも強く、耐用年数が長い等の特徴がありますが、使用する材料が多いので、コストもあがり屋根荷重が重くなるので、それに合わせた建築構造も強固にしなければなりません。
(左)平瓦 (右)丸瓦
平瓦を敷き並べて、継ぎ目に丸瓦を並べる
・引掛け葺き―屋根下地に横方向に桟木を打ちそれに瓦を引っ掛けて葺く工法です。
現在の主流の工法で、瓦がずり下がらない、瓦を釘打ち出来るなどの丈夫さを優先した工法で、耐震・耐雪・耐風の力を発揮します。

「桟木」を打ち、それに瓦の裏の凸ちんを引っ掛けて、釘で留めていきます。
「洋」
形状は、

・平板(㈱鶴弥 スーパートライ110)

・S形(石央瓦販売㈱ ニューセラS)
の、代表的な2タイプになります。
現在、新築物件の和・洋の割合は、4:6程度で洋が多いです。
シンプルなお宅が増えて来ていますからね。
工法は引掛け葺きになりますので、「和」と施工要領は一緒です。
「和」は棟が、熨斗(のし)積み、
「洋」は丸瓦のみという感じが多いです。
不定期な、屋根知識講座。またお楽しみに!!
屋根知識 第4弾
色のお話を先日させて頂きましたが、その続きで。
瓦で、色は陶器のように釉薬で付くのですが、それ以外の瓦、
今回は「いぶし瓦」です。

いぶし瓦は、お寺や神社などによく使われている瓦ですので、ご覧になった方は多いと思います。
で、色の付け方ですが、塗装みたいなモノではありません。
瓦素地の状態(粘土を素焼きした状態)をそのまま、
「燻す(いぶす)」のです。
言わば、瓦の燻製ですね。
最後に焼く時に、炭化水素を含むガスを接融させて、素地表面に炭素膜を成形させる方法です。
釉薬瓦とは違う「味」、独特の重厚感を出す瓦です。

瓦で、色は陶器のように釉薬で付くのですが、それ以外の瓦、
今回は「いぶし瓦」です。

いぶし瓦は、お寺や神社などによく使われている瓦ですので、ご覧になった方は多いと思います。
で、色の付け方ですが、塗装みたいなモノではありません。
瓦素地の状態(粘土を素焼きした状態)をそのまま、
「燻す(いぶす)」のです。
言わば、瓦の燻製ですね。
最後に焼く時に、炭化水素を含むガスを接融させて、素地表面に炭素膜を成形させる方法です。
釉薬瓦とは違う「味」、独特の重厚感を出す瓦です。
屋根知識 第3弾
二日続けての講座の時間です。
昨日の記事についての質問で、
「唐津市の山田地区は、赤瓦が多いですが・・・」
との質問を頂きましたので、
色について。
瓦の色はたくさんありますので、主な色を紹介します。
セメント瓦は塗装ですので、今回の内容からは省きます。
瓦の色は茶碗などと同じ「釉薬」という薬品で変わります。
最近の一般的な瓦の色は「銀黒」という色です。
壁の色などとの関係で無難に選ばれるようです。
この4色の中では歴史は浅いみたいです。

石州瓦の始まりは「甕瓦(カメガワラ)」と呼ばれていたようです。
甕は漬物とは漬けるアレですね。
今でも年配の方が、石州瓦の事を甕瓦と良く呼ばれます。
私が意味を知らない時は「亀瓦」と思ってました。
(亀の甲羅のように硬い瓦だから・・・?)
今、思うと恥ずかしい。
始まりの時点ではその甕の色「来待色」のみだったそうで、それで赤っぽい色が多いみたいです。
来待とは、島根県出雲地方で産出される「来待石」の粉を釉薬で使用しているので、独特の赤っぽい色がでるようです。
私もこの色は好きですね。

来待色
しかし、多彩な色がある中で最近でも山間部では赤色を使用されているのは、「山の緑」と「屋根の赤」がマッチするのでは?
と言う見解です。
集落の中で、景観を考えて同じような色にしている集落も全国にはあるみたいです。

赤色
実際、黒などの屋根でしたら、目立ちませんし・・・。
唐津市の上場地区、山田地区に多いです。
ぜひ、呼子方面に行かれる時は、海岸線ではなく、山越えで行って見て下さい。
それから、赤系は黒に比べると屋根が大きく見えるからも、あるのでは。と、私の勝手な考えです。
黒は、重厚感が出すぎるような気がします。
赤州瓦とは私は聞いた事はありませんが、唐津市山田地区は石州瓦の赤瓦だと思います。
昨日の記事についての質問で、
「唐津市の山田地区は、赤瓦が多いですが・・・」
との質問を頂きましたので、
色について。
瓦の色はたくさんありますので、主な色を紹介します。
セメント瓦は塗装ですので、今回の内容からは省きます。
瓦の色は茶碗などと同じ「釉薬」という薬品で変わります。
最近の一般的な瓦の色は「銀黒」という色です。
壁の色などとの関係で無難に選ばれるようです。
この4色の中では歴史は浅いみたいです。
石州瓦の始まりは「甕瓦(カメガワラ)」と呼ばれていたようです。
甕は漬物とは漬けるアレですね。
今でも年配の方が、石州瓦の事を甕瓦と良く呼ばれます。
私が意味を知らない時は「亀瓦」と思ってました。
(亀の甲羅のように硬い瓦だから・・・?)
今、思うと恥ずかしい。
始まりの時点ではその甕の色「来待色」のみだったそうで、それで赤っぽい色が多いみたいです。
来待とは、島根県出雲地方で産出される「来待石」の粉を釉薬で使用しているので、独特の赤っぽい色がでるようです。
私もこの色は好きですね。
来待色
しかし、多彩な色がある中で最近でも山間部では赤色を使用されているのは、「山の緑」と「屋根の赤」がマッチするのでは?
と言う見解です。
集落の中で、景観を考えて同じような色にしている集落も全国にはあるみたいです。

赤色
実際、黒などの屋根でしたら、目立ちませんし・・・。
唐津市の上場地区、山田地区に多いです。
ぜひ、呼子方面に行かれる時は、海岸線ではなく、山越えで行って見て下さい。
それから、赤系は黒に比べると屋根が大きく見えるからも、あるのでは。と、私の勝手な考えです。
黒は、重厚感が出すぎるような気がします。
赤州瓦とは私は聞いた事はありませんが、唐津市山田地区は石州瓦の赤瓦だと思います。
屋根知識 第2弾
久々の講座の時間です。
今日は石州瓦とはなんぞや。
うちの社名にも入っている「石州瓦」ですが、
石州とは、生産されている産地の名前です。

そもそも、瓦(かわら)は、粘土を混練、成形、焼成した屋根材の総称を指します。
石州瓦―島根県の石見地方(旧 石見国=石州)で生産されている粘土瓦のこと。
焼成温度が高いため(約1300℃)強度に優れており、日本海側の豪雪地帯や北海道などに使用されるように寒さに強い、硬い瓦。佐賀ですと、山地でが昔から使われているようです。
その他で、有名な産地は
三州瓦―愛知県西三河地方の旧国名三河を意味する「三州」を冠した粘土瓦を言う。
焼成温度は石州より低い。コスト的に石州より手ごろ。
淡路瓦―兵庫県淡路島で造られている瓦。
灰色した「いぶし瓦(後日解説します)」が主に生産されています。
シェアは
三州>石州>淡路>その他の産地
となっています。
以上、紹介したのが焼いて作られた瓦(陶器瓦)で、その他にもセメント瓦(佐賀市内は多いですよ)やスレートなどの屋根材もあります。
「森石州瓦」ですが、石州瓦のみ使用している訳ではアリマセンよ。
自己紹介で「瓦屋」ですと紹介すると、「造っているんですか?」と尋ねられますが、生産はしていません。施工のみです。
いろんな産地から、お客様から注文を頂いた瓦をトラックで運送されてきます。
現在でも佐賀近郊で焼いて生産されているのは、福岡の城島地方では生産されているみたいです。
意外と知らない方が多いのではないでしょうか?
専門的な用語とかが出てきて分かりにくい点もあると思いますが、バンバン質問して下さい。
なるべく噛み砕いて書き込んでるツモリですが・・・。
今日は石州瓦とはなんぞや。
うちの社名にも入っている「石州瓦」ですが、
石州とは、生産されている産地の名前です。

そもそも、瓦(かわら)は、粘土を混練、成形、焼成した屋根材の総称を指します。
石州瓦―島根県の石見地方(旧 石見国=石州)で生産されている粘土瓦のこと。
焼成温度が高いため(約1300℃)強度に優れており、日本海側の豪雪地帯や北海道などに使用されるように寒さに強い、硬い瓦。佐賀ですと、山地でが昔から使われているようです。
その他で、有名な産地は
三州瓦―愛知県西三河地方の旧国名三河を意味する「三州」を冠した粘土瓦を言う。
焼成温度は石州より低い。コスト的に石州より手ごろ。
淡路瓦―兵庫県淡路島で造られている瓦。
灰色した「いぶし瓦(後日解説します)」が主に生産されています。
シェアは
三州>石州>淡路>その他の産地
となっています。
以上、紹介したのが焼いて作られた瓦(陶器瓦)で、その他にもセメント瓦(佐賀市内は多いですよ)やスレートなどの屋根材もあります。
「森石州瓦」ですが、石州瓦のみ使用している訳ではアリマセンよ。
自己紹介で「瓦屋」ですと紹介すると、「造っているんですか?」と尋ねられますが、生産はしていません。施工のみです。
いろんな産地から、お客様から注文を頂いた瓦をトラックで運送されてきます。
現在でも佐賀近郊で焼いて生産されているのは、福岡の城島地方では生産されているみたいです。
意外と知らない方が多いのではないでしょうか?
専門的な用語とかが出てきて分かりにくい点もあると思いますが、バンバン質問して下さい。
なるべく噛み砕いて書き込んでるツモリですが・・・。
屋根知識 第1弾
今日は、屋根の形状について。
佐賀県内で良く目にする、屋根の形状として代表的なモノを3タイプ説明します。
まず、一番メジャーな
切妻屋根(きりづま)

屋根の最頂部の棟から地上に向かって二つの傾斜面が本を伏せたような山形の形状をした屋根の事を言います。
この、屋根ですと施工も簡単ですし、雨漏れ等の故障が起こりにくいです。
続きまして、
寄棟屋根(よせむね)

4方向に傾斜する屋根面をもつ形状の屋根の事を言います。
切妻造と比較して、雨の流れがよく雨仕舞いに優れますが、屋根裏の換気が取りにくいです。
最後に、
入母屋屋根(いりもや)

上部においては切妻造、下部においては寄棟造となる形状の屋根の事を言います。
複雑な構造の為に施工の手間はかかりますが、家の重厚感があります。
以上、簡単ではありますが、屋根講義第1弾でした。
次回は・・・。
お楽しみ(^^)
佐賀県内で良く目にする、屋根の形状として代表的なモノを3タイプ説明します。
まず、一番メジャーな
切妻屋根(きりづま)

屋根の最頂部の棟から地上に向かって二つの傾斜面が本を伏せたような山形の形状をした屋根の事を言います。
この、屋根ですと施工も簡単ですし、雨漏れ等の故障が起こりにくいです。
続きまして、
寄棟屋根(よせむね)

4方向に傾斜する屋根面をもつ形状の屋根の事を言います。
切妻造と比較して、雨の流れがよく雨仕舞いに優れますが、屋根裏の換気が取りにくいです。
最後に、
入母屋屋根(いりもや)

上部においては切妻造、下部においては寄棟造となる形状の屋根の事を言います。
複雑な構造の為に施工の手間はかかりますが、家の重厚感があります。
以上、簡単ではありますが、屋根講義第1弾でした。
次回は・・・。
お楽しみ(^^)